お疲れ様です。作造です。
農業生活13日目、本日は昨日に引き続き田んぼでの肥やし散布作業を行いました。
作業日誌
2022年4月13日 天気:曇り 平均気温:15℃
8:00 集合、
8:30 肥やし散布作業開始
11:45 午前の作業終了
13:10 集合、作業再開
16:00 作業終了、後片付けなど
17:00 解散
作業内容
本日は昨日に引き続き田んぼに肥やし散布(コシイブキ・早稲用)を行いました。
作業そのものは昨日と全く同じ段取りでしたので、特に新しい作業というものはありませんでした。
なお、先日からの肥やし散布作業で使っている肥やしは一発肥料と呼ばれるもので、植え付け前に撒いておけば、収穫までに施肥が不要になるものだそうです。
各成分毎に層となっている粒剤で、まずは基肥(速効性あり)の効果があり、その効果が切れる頃を分げつ肥、穂肥、穂ぞろい期における追肥と効果が発現してくるものだと教わりました。
明日から天気が崩れ気温も下がるようなので、作業後は農機具や肥料の雨対策とトラクターの洗車(田んぼの泥撤去など)を行い解散となりました。
メモ
基肥(きひ、もとごえ)
種を撒いたり植え付けを始める前に耕地に施す肥料。
分げつ肥
稲が育ってきて枝分かれを開始してから幼穂が形成されるまでの期間に施す肥料で、稲の分げつを盛んにして穂数を増やす効果がある肥料。分げつというのは稲科作物の枝分かれのことで、最初から数えて4枚目の葉がでると同時に、1葉の付け根から枝分かれし最初の分げつが発生します。その後は2葉の付け根から2番目の分げつが発生するとのことです。
穂肥
種まきからおよそ3ヶ月後、穂の分化が始まる出穂(しゅっすい)前の2~3週間前に散布する肥料で、穂の籾(もみ)を増やす効果があるそうです。
穂揃い期追肥
出穂前後から穂そろい期(出穂10日後程度)あたりで散布する肥料です。出穂後に栄養不足になると稲本体の老化が始まったりするとのことなので、これを防ぐために散布する必要があるとのことです。
感想
連日同じ作業ということで油断していましたが、今日は作業の合間に上記のような知識面でのレクチャーを受けたり、肥料袋裏面にもざっくりとですが効能を曲線で表した図が明記されていたため、それを読んでみたりしていました。
勝手な思い込みですが、農業は各農家さん毎の経験即に基づいた作業だと考えていたのですが、作物の生育状況や天候により作業が前後することはあるものの、肥料はもちろん水やりやハウス内の温度管理など、かなり細かく計算されている面が多いことを知ることができました。毎日の記録、肥料毎の効果、適正な温度や水量など覚えることや勉強することがたくさんあり、決して楽な仕事ではないと再確認した一日になりました。

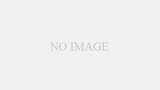
コメント